
Episode XVII : 白い風
|
「う〜ん、雪、か」 それは数年前のある日の夕方のことだった。病院に立ち寄ったあたしは、ふとしたきっかけでその話題について話し合っていた。 大池先生がなにやら難しそうな顔で腕組みをして、眉をぎゅっと寄せる。どこか大げさなその表情がちょっとおかしくて、あたしは小さく笑っていた。 そんなあたしに気づいたのか気づかないのか、しばらくして大池先生が口を開いた。 「さすがに北海道に行けば、まだ見られるんじゃないかな。昔はあのあたりの気温は簡単に零下十度とか二十度とかまで下がったし、温暖化と言っても雪が降らなくなるほどじゃないだろう」 「それにしては見ないよね。聞いたら、富士山頂も雪が無いんだって」 「ふぅん。それは気候の問題じゃないかな。気温だけなら雪が降ってもおかしくはないと思うね」 大池先生の言葉は、いかにも学者らしい慎重な表現。ふと先生が、他の学者仲間と難しい問題について語り合うときのことを思い出す。まぁ、この言い回しはある意味、仕方のないことだろう。なにしろ、こんな議論をしたところで、実際に検証のしようがないのだから。 「しかし、どうしたんだい、急に」 「うん。この前ユズハさんと話をしてたら……、そうだ、ユズハさんのこと、話したっけ」 「「わかやまの国」に住んでいるロボットの人だろう? ああ、聞いているよ」 「そのユズハさんは、雪が降るのを見たことがないんだって。あたしは一度だけあるんだけど、そのときの絵を分けてあげたらすごく喜ばれたんだ」 「まぁ、雪を知らないロボットの人なら、たくさんいそうだね」 「うん。あたしはほんとに初期の型だし、日本中あちこち言ってるから。奥羽とか日本アルプスの積雪も覚えてるんだ。ユズハさんはだいぶん後期の型で、しかもずっと大阪から「わかやまの国」にいたから、仕方ないかもね」 「ま、どちらにしてもこれからはまず無理かも知れないね」 「でも、ちょっと不思議。そう言えばさ、代わりに雨は多い気がしない?」 「う〜ん……」 このちょっとした話題は、いつものようにすぐに別の話題に移り、あたしはなんとなくそれを忘れてしまった。そしてその話題は、記憶の奥のどこかに隠れ、ずっと顔を出すことはなかった。 そんなある日。 その日は久しぶりに寒かった。アキオがひどく欲しがっていた本が入るという話を聞いたうえ、別の本屋に渡す本がたまっていたあたしは、古本市の日にあわせ、その前日から久々に「みやこ」に出かけることにした。 早朝の市に出て、そのまま「みやこ」の南部から「ならの国」まで配達。夕方にユズハのところに着いて一泊させてもらったあと、翌日の朝に家路についた。 本当にびっくりするほどの冷え込みで、あたしはもっと厚手の上着を持ってくれば良かったと、そんなことを考えていた。 いつものように生駒山から宇治を回り、「みやこ」の南端をかすめてから六甲山の尾根を走るコース。そろそろ宝塚のあたりも川を渡る橋が危なくなっていて、新しいコースについて悩むことになった。 そうやって六甲山頂を越えたのは午後を回ってから。いつものように重量物を積んで、車は辛そうだが、気温が低いおかげで少し走りやすい。いつもより少しだけ力が出るし、オーバーヒートも遅くなる。 尾根道の北、有馬側は黒っぽい雲が出ている。雨でも降っているのでは、そんな印象。南の神戸の市街地側は薄曇り、というより晴れ間すら見える天気だ、いつものことながら、山一つ越えると天気が全然違うのが面白い。 尾根沿いの道から左折して山を下るワインディングに入ったころには、車には淡い日の光が当たっている。雨に降られることはなさそうだと少し安心したあたしは、視界がかすかに白っぽくなって来たのに気づいて、少し眉をひそめた。 「霧? やだなぁ、こんな時に」 車はちょうど、道の途中に作られた駐車場に差し掛かっていた。少し疲れが出ていたし、こんな状態で視界の悪い山道を走るのも危ない。そう考えたあたしはその駐車場に車を乗り入れた。 ふぅ、と、そんなひと息をつき、本の山の上で丸くなってるベータを少し見やりながら小さく体を伸ばす。外で身体を動かそうか、そう考えながら視線を上げたあたしは、窓の外の様子が少しおかしいのに気づいた。 霧と言うより雨に見えなくもない。しかし、雨特有の黒っぽい色合いがない。 やがてフロントガラスに、いくつかの水滴が着く。やはり雨だろうか、そう思ったあたしは、次の瞬間、車の周りを白っぽいものが包んでいるのに気づいた。 一瞬、何が起きているのかわからない。霧とは違う、もっとはっきりとした白。それが、背景の山肌の黒っぽい色としっかりとした対比を見せている。 それらは、かすかな日の光に照らされて、宙を舞っている。唖然として見ているあたしの前で、あっという間に視界いっぱいに広がる。 まさか、そんな思いで改めて窓の外を見る。そして、それがあたしの見間違いでないことを確信すると、車の外に飛び出して、あたりを見回した。 そうしている間にも、それはどんどん増え、風景の色が一変する。ようやく事態に気づいたあたしは、思わず息をのんでいた。 「これ……雪?」 ようやく口からその言葉が出る。が、自分で言っておいて、自分で信じられなかった。 それでも、あたしが見ているものは、雪に間違いなかった。それ以外に考えられない。いや、これは明らかに雪だ、そう自分に言い聞かせる。 状況が理解できるまで、たっぷり一分はかかった。 「ほんとに……雪なんか降るんだ」 そうつぶやいて、あたしは駐車場を歩きながらあたりを見回した。気候の問題だ、大池先生が言っていた言葉を思い返して、自分を納得させようとするが、それでもまだ、自分が夢を見ているのではないかと、そんなことを考えてしまう。 降っている雪は、一つ一つがびっくりするほど大きい。雪というのはこんなものだったのだろうか、そんなそんな気持ちになっている。 その雪は、降ると言うより、風に漂っている感じだ。地面はかすかに湿っているだけ。雪が積もりそうな様子はない。それがあたしから現実感を奪う。顔に当たる雪の粒は、なぜか全然冷たくない。油断すると、まるで綿ぼこりが待っているように思える。しかし、手のひらに乗った雪は、ほとんど瞬間的に小さな水滴になって、あたしの錯覚を否定する。 駐車場の一角は展望台になっている。しばらく周囲の雪に気を取られていたあたしだったが、ふと思いついてそちらに足を向け、下に広がる神戸の街のほうへと目を向ける。しかし、その眺めはすっかり煙っていて、かわりに、粒の一つ一つまで見える雪たちが、山の尾根の間を舞う風を忠実に再現している様に、思わず目を奪われる。 暗い緑色の稜線と、白い雪を含んだ風。その風が一斉に斜面を駆け下りる。しかしその先の神戸の街は、まだかすかな陽光に照らされて白い。雲の切れ目から漏れる陽光の形が、雪を照らしてはっきりと形を見せる。 幻想的な風景。寒さも感じない。ただ、真っ白な風に包まれる。有馬側で降った雪が、季節風に乗って一気に斜面をおり、神戸に届く。 冬の手紙。日の光に照らされてきらきら光る。 いつもとあまりに違う風景。それに偶然出会えた自分の運の良さがうれしくなる。 白い風は刻一刻と変化する。風の音も感じない無音の世界。なんとなく涙が漏れそうになって、あたしは慌てて目頭を押さえる。 あたしはその場から動くことができなかった。ただひたすら、風の中に立っていた。 あたしは、あの札幌での出来事を思い出している。まだ、にぎやかだったあの時代の名残が残る札幌の街。 春先の雪。視界を白く覆い尽くす。時々通る車は、さぁっ、という流れるような音を立てるだけ。まばらな人混みは何の音もたてず、無声映画を見ているように錯覚する。静寂が街を包んでいる。通りも街灯も街路樹も、建物も看板も、みんな真っ白な雪に包まれている。 このごろすっかり、人も少なくなったね。人も車も街の灯も。先生がそう言う。どこか寂しいそうに。 夜闇に包まれた街路。街灯の光輪を無数の雪の影が横切る。 あたしが特別に鮮明に思い出せる印象の一つ。 その思い出は、先生や研究室の人たち、そして、一緒に仕事をしたロボットの友達、みんなが最後にそろって遠くに行った、その思い出でもあった。みんなそのことがわかっていて、精一杯、一緒の時間を楽しんでいた。あたしと友達は初めて乗った飛行機で浮かれていたし、札幌についても、本来の目的の学会そっちのけでおいしいものを食べに行ったりした。 その思いが、不意に心の中に満ちてくる。なんとなく暖かいようで、寂しいようで、また涙が出てくる。 あのときとは違う、ただ、雪という共通点だけ。でも、そのたった一つの共通点が、過去への心の扉を大きく開く。たくさんの思い出の一つを呼び覚まし、次々と連想を生んで広がってゆく。あの時の気持ちはずっとあたしを包んでいる。 あたしはただじっと、その思いに身を任せていた。 じっと。ただ黙って。 六甲の雪は半時ほどですっかり上がっていた。もう白い綿は降りてこないことを確認して、あたしは大きくため息をついた。 神戸にはお天気雪が降る、そんな先生の言葉を思い出していた。 そして、自分がそんな街に住んでいることが、少しうれしくなる。 しばしその余韻を楽しむ。神戸の街が再び日の光の中に浮かび上がる。まるで自分が幻覚を見ていたのではないかと感じる。しかし、全身がかすかに濡れ、寒さを感じ、それはが間違いなく自分がそこにいた証拠のように思えた。 もうひとつ大きなため息。改めて、もう雪は降らないことを確かめ、ゆっくりと車に戻る。どうやら眠っていたらしいベータが、大きくアクビをし、本の表紙に爪を立ててのびをする。 「もう、すごいもの見てたのに、もったいないぞ」 少し冗談めかしてそう言ってみる。 エンジンをかけて駐車場を出る。かすかに濡れた路面を静かに下る。街並みが刻一刻と近づいてきて、現実感がもどってくる。街並みの中に入る頃には、あたしの意識はもう、普段の生活に戻っていて、そのことになにか不思議な感情を覚える。 店に帰るまでに小半時ほど。ガレージに車を入れ、積んできた黙々と本を降ろしていると、バイクの排気音が坂を登ってくる。アキオだ、あたしはすぐに気づいて、急いで彼から頼まれた本を引っ張り出すと、それを手に表に顔を出した。 「ふわぁ、ばり寒いわ。みかげ戻ってきとってよかったわ、夜やったらどうしよかと思うとった」 ちょうどそのときに、アキオがバイクを停める。あたしは本を彼に見せながら言った。 「いま帰ったところだよ。ほら、『アルジャーノンに花束を』」 「へへへ、これ、前から読みたかってん」 アキオがポケットから財布を財布を引っ張り出す。代金を受け取って簡単に確かめる、引き替えにあたしが本を渡すと、アキオはうれしそうな表情になった。指先で軽く表紙をなでながら、じっと見ている。 「それにしても今日は寒かったよね。雪まで降っちゃって」 最初の数頁をめくっていたアキオを見ながら、あたしがそう言うと、アキオは理解できないと言った表情であたしを見た。 「雪? 雪ってなんや」 「え? 降ってなかった? すごかったけど」 「降ってへんで。雪なんて降るんか?」 「…………」 話が食い違っているようで、あたしたちは数秒ほど、目をしばたたかせて互いを見ていた。その食い違いに先に気づいて口を開いたのはアキオだった。 「ほ、ほんまに雪、降ったんか?」 「あ、うん。山の上で見たんだけど。あれ、こっちはどうだったの?」 「ちぃっと、お天気雨があったで。霧雨みたいなん」 「あ……」 そうだ、六甲山は九百メートル以上もある山だし、あたしがいた駐車場ですら標高は七百メートルに近い。これだけの標高差で、雪が霧雨に変わってしまったのだ。 つまり、雪を見られたのは、山にいたあたしだけ、ということなのだ。 「そっか、こっちじゃ雪じゃなかったんだ」 あたしが少し残念になってそう言ったが、アキオはそれどころではなかった。あたしが本当に雪を見たことにようやく気づいたアキオは、大きく目を見開いて、数秒ほど言葉をためていたかと思うと、猛烈にしゃべり出した。 「みかげ、雪見たんか」 「あ、うん、すぐやんじゃったけどね」 「山のほうやろ? そ、それ、積もっとぅ?」 「ううん、全然。地面が少し濡れただけかなぁ」 「あ〜っ 俺も雪、見たかったわ。みかげ、なんで呼んでくれへんの」 「そ、そんな無茶なこと言われたって……」 アキオの理不尽な文句に、あたしはちょっと困ってしまう。アキオはさも口惜しそうに、文字通り地団駄を踏んでいる。そろそろいい年なのに、なんだか、まだまだ子供っぽいところが抜けていない。 というより、男の子というのはこんなものなのだろうか。あたしは思わず、小さく苦笑してしまう。 しかし、続くアキオの言葉に、あたしはつい、はっとなってしまう。 「ずっこいで、みかげは雪くらい見たことあるんやろ。俺、一生に一度かもしれへんかったんやで」 「あ……」 確かに彼の言うとおりだ。今も気候は年々暖かくなっているし、このままでは本当に、雪など二度と降らない、ってことになりかねないだろう。 彼に雪を見せる、本当に最後の機会だったのかもしれない、そう考えるとあたしは、ちょっと気分が落ち込む。 「あのさ、ごめんね、アキオ」 あたしが、しゅんとしてそう言うと、今度はアキオは、面食らったように口を閉じた。またあたしを見ている。 「なんや、みかげ、変やで」 「は?」 「いつもやったら、「いいだろ〜」とか言うて自慢しとうとこやろ」 「……なにそれ、あたしそんなことしないよ」 「そか? そらみかげの思い違いや」 「も〜っ!」 あたしが頬を膨らませて、わざと大きな仕草でアキオの背中を叩こうとすると、彼はひょい、と身をかわしてしまう。あたしはちょっとムキになって彼を追いかけて、アキオは面白そうに逃げ回る。 ちょっとだけ、なんだか数年前にもどったような、そんな気分になっている。さすがに互いに照れくさくなって、じゃれあいはすぐに終わってしまう。 「あのさ、ほんとにごめんね」 「ええて、別に。雪くらい見いへんかったって、死にはせんやろ」 「ほんとに、あたしじゃなくてアキオが見たんならよかったのにね」 「ま、それは正直なとこやけどな」 結局、雪の話はそれっきりだった。アキオはあたしが持って帰った本を持って嬉々として帰っていった。坂を下っていく彼のバイクを、あたしはため息をついて見送った。なんだか少し動きたくなくて、アキオが見えなくなってもあたしはまだそこにいた。 そして、改めて六甲山を振り返るが、そこにはかすかに煙った稜線と、そのむこうの雲が見えるだけだった。そこにはもう、あの光景の名残すらなく、自分が夢を見たのではないことを自分に言い聞かせるのに少しだけ時間を使った。 あたしが最後に見た雪は、アキオを思うちょっと心苦しいような感情と共に、あたしの大切な思い出の一つになっていた。 |
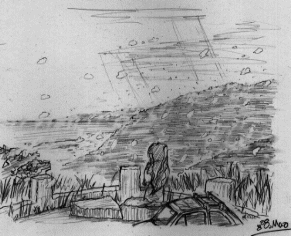
|